サントリーホールで奏でた“Freude(歓び)”の旋律 ー特別な瞬間の裏側
2025/05/30
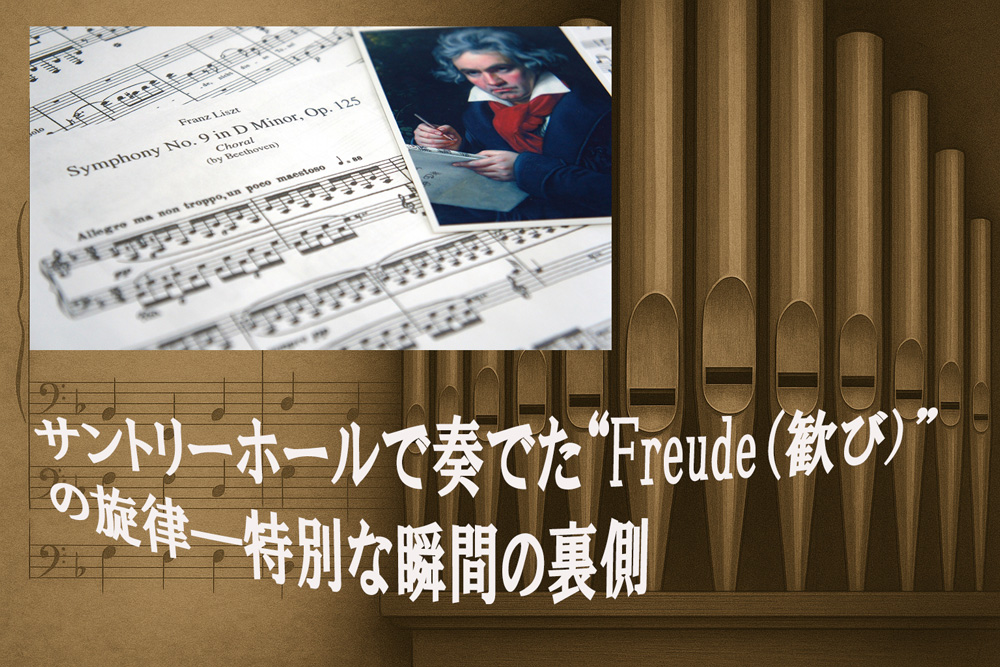
青山学院の150周年記念事業に何か関わりたいと思っていたところ、Iさんから「サントリーホールで第九を歌う企画がある」と教えていただきました。話を聞くと、参加にはいくつかの厳しい条件があり、譜読みができること、ドイツ語で第九を歌えること、秋から始まる月3~4回の練習に7割以上参加できること、そして本番では暗譜が必須。胸が高鳴るのを感じながら、サントリーホールの客席から見る舞台に立っている自分の姿を想像しつつ、家へ帰りました。そして、「この条件をクリアできるのか?」と自問しながら、家族に相談したのが2024年4月末のことでした。こうして、新たな挑戦への第一歩が始まったのです。
「第九」といえば、年末に耳にするあの壮大な曲です。しかし、ドイツ語で歌ったこともなく、歌詞すら知らない私にとって、数か月で歌えるようになるのかは大きな挑戦でした。そこでIさんから教えてもらった渋谷区主催の「第九初心者講座<基礎練習>~第九を歌えるようになる!~」(以下、初心者講座)に、迷わず申し込むことにしました。
6月からの2か月間、毎週土曜日の午後は「第九」の時間となりました。
私のパートはソプラノ。誰もが知る旋律が含まれているとはいえ、約25分もの長さを持つこの曲を、週1回2時間半の練習だけで習得するのは容易ではありません。さらに、高音域が続くため、講師からは「ご近所さんに通報されるので、ソプラノの方は家で練習しないでください」と冗談交じりのアドバイスが。受講者の中には、一人カラオケで練習する人もいましたが、私は通勤時に必ずYouTubeで音源を聴くと決めました。電車の中では楽譜を見ながら、歩いているときはソプラノパートの音源を聴きながら、マスクの下で口をもごもごと動かし、難しい部分は自宅で楽譜と向き合いながら繰り返し練習しました。
そんな中、渋谷区の同じ講座に参加していた本学のSさんとの出会いがあり、平日のお昼休みに一緒に練習することに。幸運にも、高音を出しても通報されない17号館の器楽練習室を借りることができました。挑戦の第一歩は、楽譜を見れば一通り歌えるレベルにまで到達したのでした。
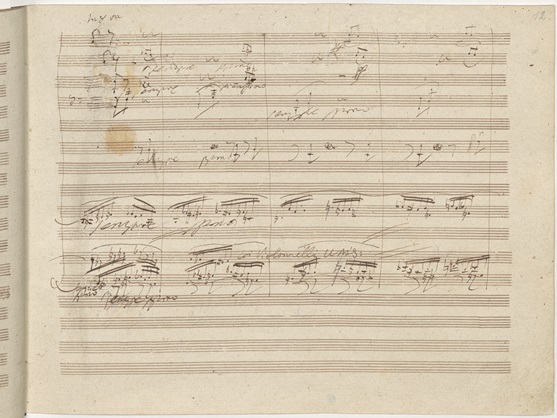
次の課題は暗譜でした。しかも、最終目標とする舞台は天下のサントリーホール。カラオケ気分で歌うわけにはいかず、観客の期待に応えるためにも、しっかりと準備をしなければなりません。そこで、舞台に立つ度胸をつけるためにまずは、「渋谷区民音楽のつどい〜みんなで第九を」という12月の演奏会に向け毎年募集される渋谷区の合唱団に参加することに挑戦。期間は3か月。会場は約2000人弱を収容するLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)。講師の熱意もひしひしと伝わってきます。
この講座では、歌詞の意味を理解しながら歌うことに加え、身体を楽器として使う方法を実践していきます。丹田を意識し、喉の奥を広げ、口を縦に開けて遠くへ声を届ける——そんな技術を身につけることで、より響きのある歌声を目指します。さらに、練習後に声をからしてしまう私に、毎年参加しているベテランの方からも貴重なアドバイスをいただきました。「ハミングをしながら眉間から音を出すようにすると鍛えられるよ」との助言を受け、私はお風呂でのハミングを習慣に。家族は、私が毎日ご機嫌なのだと思っていたかもしれません。
初心者講座のときから、息継ぎのタイミングや歌うときのコツなどをたくさん書き込んだ楽譜が、私にとっては心の支えでした。その楽譜を持たずに歌うことに対してずっと不安がつきまとい、暗譜ができているところとそうでないところが混ざったままの日々が続いていました。
そんなある日の練習帰り、
「楽譜を持たずに歌ってみたら、指揮がよく見えて、すごく歌いやすかったよ」
とSさんが言うのです。その言葉に背中を押され、思い切って楽譜なしで歌ってみることに。すると驚いたことに、視線が自然と指揮者に向き、細やかな指示がとてもよく見えるようになりました。これまで気づかなかったタイミングや表現が、まるで目の前で解き明かされていくようでした。そして気づけば、いつの間にか暗譜も自然と身についていました。
あとは場数を踏んで慣れるだけ——そうして迎えた初舞台となる「渋谷区民音楽のつどい〜みんなで第九を」当日。オーケストラと指揮者の呼吸に合わせて歌う心地よさと一体感は、楽譜に頼っていたころにはなかった新しい楽しさでした。
2024年の夏、ついに「みんなで第九を歌おう合唱団」の団員募集がスタートしました。サントリーホールで歌う——そんな夢のような舞台に立てるチャンスを前に、私はまだ「第九」の暗譜が完全にはできていなかったものの、思い切って応募することにしました。締め切り日の1週間以上も前に「現時点で募集人数を超えており、抽選となります」とのメールが届き、その人気の高さを実感しました。それだけに、団員として参加できることは本当に幸運で、喜びもひとしおでした。
この合唱団は、青山学院に関わる人たちによって特別に結成された153名のメンバーで構成されています。現役の大学生、幼稚園から大学院までの卒業生、保護者、教職員など、世代や立場を超えた“青学ファミリー”の誕生です。
練習は全17回。1回あたり2時間半から3時間と、本格的な内容です。主な練習場所は青学講堂ですが、940教室や総研ビルの11階・12階を使用することも。入試期間中には、学外の徒歩圏内の施設を使うこともありました。
会場に着くと、まずは受付で名札の裏にあるバーコードをスキャン。これで出席が記録されます。名札の表には、名前、担当パート(ソプラノ、アルト、テノール、バス)、そして学院との関係が記されており、初対面同士でもすぐに会話がはずみそうです。
練習の流れは、まず準備体操で身体をしっかり動かして血流を促し、その後ピアノに合わせた発声練習へ。毎回このルーティンからスタートし、本格的な練習へと入っていきました。
サントリーホールでの本番を目指して、世代を超えた仲間たちとともに声を重ねていく日々。その一歩一歩が、かけがえのない経験として積み重なっていきました。
本演奏会で指揮をしてくださる予定でありました秋山和慶先生が、1月26日夜に入院先の病院にて84歳にて永眠されたとのお知らせがありました。年明けにご自宅でお怪我をされ、療養にお時間がかかるとのことで指揮者の変更のお知らせがあった矢先のことでした。お怪我が治られた頃に、今回の演奏会を何かの折に聴いていただく機会があったらと誰もが願っていたと思います。1月31日の練習会場では、一同悲しみに包まれていました。
「同じ曲でも、指揮者が変わると、まるで別の曲のようになる」——今回の150周年記念演奏会の「第九」では、それを初めて実感しました。
以前、渋谷区主催の講座でようやく身についてきた歌い方が、今回の合唱ではことごとく通用しないことがわかり、最初は驚きと戸惑いの連続でした。使用する楽譜も、それまで慣れ親しんだものではなく、まったく新しい指定楽譜に切り替え。ページ構成が違うため、「●●小節目から!」と指揮者の指示が出たらすぐに歌い始められるよう、小節番号を書いたインデックスを貼って自分なりにカスタマイズし直すところからのスタートでした。
それでも、一からやり直す価値がありました。当初予定されていた指揮者の秋山和慶先生の音楽づくりに合わせて、合唱指導を担当された小林昭裕先生は、よりドイツ語らしい発音や細かなニュアンス、テンポの取り方など、次々と新しい視点を教えてくださり、その都度、まっさらな楽譜に自分なりに書き込んでいきます。 “新たな学びの発見”という感じでした。
なかでも印象的だったのは、ソプラノパートへのアドバイスです。「この曲には尋常でない高音が多く出てくる。五線譜を超えるような高音については、無理に歌詞を発音しなくていいので、まずはしっかりと音を出すことが大事」という言葉に、心が軽くなりました。旋律としての音をしっかり響かせることができれば、その部分は他のパートが丁寧に歌詞を歌うことで補ってくれるというのです。高音での歌詞を発音することが難しいと多々感じていた私にとって、このアドバイスは救いとなりました。
秋山先生に代わり冨平恭平先生が指揮を務めることになると、これまでの指導内容ともまた異なる部分が出てきました。たとえば、これまでは「余韻を大切に」としていたフレーズが、冨平先生のもとでは「迷わずスパッと終わる」スタイルに変更となりました。スピード感のある進行に、一瞬たりとも気を抜けません。再び、新たに書き込んだ楽譜から目が離せなくなってしまいました。
団員の何人かの方が「まるで学生時代の部活みたい」と表現していましたが、まさにその通り。練習は本気そのもので、心も体もフル回転です。
どのくらいのスピード感だったのか。個人的な感想にはなりますが、冨平先生が指揮を振る「第九」第4楽章は、驚異的なテンポで駆け抜けました。通常、約24〜25分ほどかかるところを、20分強という速さで完奏。演奏会後に開催されたレセプションでは、作曲家の渡辺俊幸先生が「私が経験した中でも最も疾走感あふれる素晴らしい『第九』だった」と語っていらしたのがとても印象的でした。
本番前日、練習会場では緊張感と高揚感が入り混じる最終リハーサルが行われました。
青学講堂でオーケストラが最後の仕上げをしている間、合唱団は、その階下の旧短大地下食堂で、カレッジソングに加えて、本番当日の入退場の動きや注意事項など細かく確認していきます。

まず、自分が何列目に立つのか、隣の人が誰かを確認します。その後、上手(テノール・アルト)と下手(バス・ソプラノ)に分かれ、4列ずつの計8グループが作られました。各グループの先頭にはプラカードが掲げられ、入退場の動きをしっかりと確認しました。一人ひとりに立ち位置の番号が書かれたシールが配られ、その場で名札に貼るよう指示されました。本番当日もこの名札を必ず携帯するように、という注意が加えられます。
ア・カペラで歌う「カレッジソング」の最終練習にも熱がはいります。練習当初から学生指揮者・青島芹奈さんが丁寧に指導してくれたこの曲。青山学院の昼休みによく耳にするこのメロディを、自分たちが歌えるという喜びを噛みしめながら、歌詞一つひとつに想いを込めて歌いました。そのたびに、先輩たちの母校愛が静かに、しかし確かに胸に伝わってくるような感覚がありました。
舞台衣装については、以下の案内がありました。
注意事項を読みながら、「ポケットチーフとして白色のティッシュペーパーで代用できるのか!」「女声、男声と記載してある!」等とちょっとした興味深い発見がありました。
注意事項の確認後、青学講堂に移動し、青山学院管弦楽団の学生たちとの最後の“オケ合わせ”へ。今回で3回目となる合同練習でしたが、そのオーケストラの仕上がりは素人の耳にもはっきりわかるほどの完成度。彼らが重ねてきた練習の努力が、音の一つひとつに込められていました。
そのときふと、練習中の冨平恭平先生の言葉を思い出しました。
「第九を歌う人たちは、何年も歌ってきているからこそ、癖がなかなか抜けない。けれど、今回初めて『第九』に取り組む学生オケは、素直に吸収していくから、ぐんぐん上達しています」
なるほど、指揮者から見れば、経験豊富な団員で構成された合唱団ほど“修正”が難しいのかもしれません。それだけに、これまで私たちをまとめてきてくださった小林先生や冨平先生のご苦労も、改めて胸に迫ってきました。

この日、ソリスト4名との初合わせでもありました。プロの歌手たちが放つ圧倒的な存在感と、美しい歌声。聴き惚れながらも、「いよいよ明日は本番」という実感が、じわじわと湧いてきます。
明日は団員の方たちとここまで積み重ねてきた練習が実を結び、最高の一日を迎えられますように。
2025年3月16日、演奏会当日は冷たい雨模様となりました。サントリーホール隣のテレビ朝日前のアーケードの下に朝9時に集合です。皆気合が入っているからか、集合時刻より前には、すでにアーケードの下は合唱団員でいっぱいに。

点呼が終わると入館証が配られ、自分のグループのプラカードを目印にしてサントリーホールへと向かいました。


サントリーホールに到着すると、まずは1階の客席からステージ袖口へ移動する入場練習が行われました。舞台裏へ進む際は、目的地はわかっていてもそこまでの道順を知らないため、自分の隣で歌う人の背中を見失わないように注意しながらひたすら進んでいきました。
スタッフの合図で4列目と2列目が同時に入場、続いて3列目と1列目が入場します。それぞれの列がそろってから列ごとに着席していきます。また、自分の立ち位置から指揮者が見えるか確認します。ステージ上の各列の段差は思いのほか高く、3~4人掛けのベンチ椅子は背もたれもなく固定もされていないため、一番上の列ともなるとバランスを崩したら背中から落下して大惨事になりかねません。同じベンチに座る仲間たちと「後ろに体重をかけないように座ろう」というちょっとした注意が必要でした。

あらためて周りを見回すと、ステージを囲むように360度の方向に客席があります。たしかチケット発売当初、座席表の埋まり具合をみたとき、ステージ後ろの客席は、あまり埋まっていなかったのであまり人気がないのかと思いましたが、実は、一番ステージに近く、指揮者もよく見えて、演奏者と一体感を味わえるお得な席なのかもという発見がありました。

このあとは、リハーサルルームに入って、お決まりの体操と発声練習です。昨日の注意書きにもあった通り、リハーサルルームは153名の合唱団員にはとても狭く、真ん中あたりにいるだろう合唱指導の小林先生の姿が見えません。先生の声を頼りに発声していきます。カレッジソングを1回歌って気持ちを盛り上げたところで、小林先生から頂いた本番に向けての熱い激励のお言葉に胸が熱くなりました。
舞台でのリハーサルも無事に終え、気が付けば時刻は13時15分。いよいよ、開演です!
演奏会は第1部、第2部で構成されており、私たち合唱団は第2部に出演します。
簡単に昼食を終えてからリハーサルルームに戻り、ここから約2時間半もの待機となります。リハーサルルームには153名が座る広さはないため、この部屋の通路にスペースを見つけ、各自持参した折りたたみ椅子やレジャーシートに座ります。この間楽譜を見直したり、近くにいる方とおしゃべりしたりして、練習でお話したことのなかった団員のお人柄を知るいい機会となりました。また、待機中は、舞台での音や映像が入ってこないので、初等部から大学生までが心を一つにして奏でる第1部は、どれほど透き通ったハーモニーがホールで響き渡っているだろうかと想像したりしていました。

そして、長かった待機時間中に合唱経験の豊富な方々からいただいた、いかにも効用のありそうな飴で喉を潤したところで、いよいよ私たちの出番です。第2部はカレッジソングから始まります。いざ本番で舞台に立つと、降りそそぐ照明の向こうに、客席がぎっしりと埋め尽くされている光景が目に入りました。
前々日に団員たちに配られた「当日の手引き」の詳細欄には、「2階後方の方々に歌声を届けてください」とだけ記されていました。学生指揮者の青島さんからのアドバイスを思い出し、ア・カペラならではの調和の響きを通して、カレッジソングの歌詞に含まれる想いを客席に届けました。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、私たちが一般的に「第九」と呼んでいるこの曲は、「交響曲第9番ニ短調作品125」という正式な作品名があり、第1楽章から第4楽章で構成されています。あの誰もが耳にしたことのある有名な「歓喜の歌」の合唱が最後の第4楽章となります。
カレッジソングを歌い終え、私たちは一度退場しました。第3楽章までの間はまたリハーサルルームで待機します。ここからの舞台の様子はわかりませんが、これまで懸命に練習を重ねてきた青山学院管弦楽団の現役の学生たちは、きっと、ベートーヴェンの想いが溢れ出す第4楽章のクライマックスに向けて、丁寧に旋律を紡いでいるに違いありません。
そして第3楽章が終わるのを待って再び入場した「第九」第4楽章。冨平先生の指揮のもと、これまで積み重ねてきた練習のすべてを出し切り、壮麗なサントリーホールで卓越した音響に包まれながら、最高の指揮者、最高のオーケストラ、そして最高の仲間たちと一体となって歌い上げました。
“Freude(歓び)”の旋律でホールを満たし、演奏を終えた瞬間、会場は大きな拍手に包まれ、達成感と喜びで胸がいっぱいになりました。一生忘れることのできない、特別な経験となりました。
「―響け、青学マインド。―」どうか客席の方々にこの想いが届いていますように。

ご参考:
指導者からの話では、「第九」は世界の国々の中でも日本で一番歌われているそうです。
確かに合唱団で出会った方々の中には、年に何度も「第九」を歌いに行くというベテランの方々がいらっしゃったのに驚いたほどです。