江戸東京②「浅草巡検」【青山学院中等部3年生選択授業】
2025/10/24

1971年に始まった中等部3年生の「選択授業」。中等部生たちの個性をいかし、将来の可能性を伸ばすよう、様々な分野の授業を用意しています。
詳しくは、まとめページをご覧ください。
今年は小川広記先生(歴史)と水野祐輔先生(地理)のタッグによるコラボ授業「江戸東京」にスポットを当てています。
6月には「日本舞踊」の授業を取材し、記事にしていますのでぜひご覧ください。
今回は4年ぶりの“ブラミズノ”、浅草の巡検に同行しました。
2025年10月8日
12:45 社会科演習室に集合

お昼休みの時間は12:30から。先生も生徒も、短時間でお昼ご飯を食べてからの集合。
この部屋でパンやバナナを食べている生徒もいる。日焼け止めを塗っている生徒も。
水野先生、小川先生、生徒14名(男7名、女7名)が集まった。
先生から、今日巡検する場所を表した地図と、古地図が配布された。

12:55 中等部の大階段下へ移動
水野先生から、放課後に関する諸連絡が伝えられる。
12:58 出発

表参道駅に向かって歩きながら、生徒たちは、今年6月の巡検「四谷・永田町」のときのことを振り返っていた。暑い日で、水野先生は、家にあった保冷剤を山のように用意していったそうだ。
表参道駅に到着、交通系ICカードにチャージする生徒。
13:14 銀座線に乗車
新橋駅で都営浅草線に乗り換え

13:34 都営浅草線快速に乗車
車内で生徒が「都営浅草線は線路が広くてでかい」と感想を述べていたところ、小川先生から「銀座線は歴史が古いぞ」と一口メモ。
4限の国語の授業で出された、今日中に提出が必要だという宿題を車内で立ちながらこなしている生徒もいる。隣にはフォローしてくれる友人。
13:44 浅草橋駅に到着
ホームに掲げられた地図を見て、今どのあたりにいるのかを確認する生徒たち。

今回の巡検では、水野先生が主導し、小川先生は引率に徹し、はぐれてしまう生徒が出ないよう殿(しんがり)を務める。心強いコンビネーション。
13:47 地上へ
先生から生徒へ巡検の心得を伝達。
最初に歩く地帯は、人形や布関係のお店が多いとのこと。
水野先生は、「“人形の久月”(あのメロディで)のCMを見たことがある人?」と聞くものの、知っている生徒はおらず。
「YouTubeでは流れないか。じゃあ、“顔が命の吉徳”(あのメロディで)も聞いたことがないかな?」
やはり誰も知らなかった。同行した取材班は皆知っているのだが……。
「この辺には五月人形や雛人形などのお店が多くあります。また、ハンドメイドのビーズなどの手芸品のお店もいくつかあリます。そういった様子を見ながら歩いてみましょう」

13:51 浅草の町の巡検スタート

通り沿いや横道にも“人形”の文字が入った看板が見られる。
手芸関係のお店も立ち並ぶ。
扇子のお店を通過。「ほしい」という男子学生の声が聞こえてくる。
古くからの佃煮屋さんがある。
須賀神社の前で立ち止まり、これまで通った街並みを振り返る。

「手芸や包装紙、造花の店などの問屋さんが多くありました。このあと蔵前までは、また違った店が見えてきます。何に変わるか見ながら歩きましょう」
「佃煮の発祥を知っていますか?」
生徒は知らない様子。小川先生が「徳川家康が、摂津の国に住んでいた漁師を今の佃島に連れてきたのが始まりです」と披露。地理と歴史のコラボレーションは最強だ。
水野先生は巡検に際し、トイレや休憩場所を確保するために事前踏査をする。去年も実施した浅草巡検のため、順調で余裕を感じる流れだ。
2日前は「雨」の予報だったが、打って変わって快晴。若干汗ばむ陽気で、生徒から「水を買っていいですか」との懇願が。「無料の給水機がある雷門まで待ちなさい」と水野先生。
「蔵前が近くなりました。問屋さんの種類が変わってきます。蔵前の名前の由来を考えながら歩きましょう」
生徒たちは歩きながら、蔵前の名前の由来を友達と考えあっている。
「蔵の中は、お酒? お米? 俵?」
古いおもちゃ屋や花火屋が立ち並んでいる街並み。

そんな中、カヌレのお店が。
店の前を通ると「おいしそう」と女子生徒の声。
その声に導かれ、取材班もついついお店の前に進み、種類や値段を確認。かぐわしい香りを吸い込む。

混まない場所で立ち止まり、皆で歩いてきた街並みを振り返る時間。


「どんなお店が多かった?」
生徒からは、おもちゃや花火の問屋が多かった、との回答。
「昔ながらのおもちゃ屋や花火屋があったり、新しいカヌレのお店やカフェなどができていたり、更新が進んでいる町です」
「ところで、なぜ“くらまえ”と言うか、わかるかな?」
「蔵の前だから」
「そうだけど(笑)、蔵には何が入っていたでしょう?」
生徒「お酒?」
「それでは古い地図を見てみましょう。16番の古地図を見て」
みんなで地図を開く。

「松平だ」という生徒の声も。武家屋敷も記されている。
「“浅草御蔵”と書かれています。小川先生、蔵には何が入っていたのでしょう?」
小川先生「江戸時代、主にお米が入っていました」。
年貢米として集めたお米が蔵に収められ、付近には米問屋や札差商人(両替)が集まり、その蔵の前の場所を「御蔵前」→「蔵前」と呼んだそうだ。
「今では蔵は残っていないけど、名前が残っています。それではもう少し歩いていろいろなお店を見てみましょう」
やがて、「泥鰌(どじょう)だ」と生徒が指をさす方向に“どぜう”と書かれた風情のあるお店が見えてきた。
と、その手前の道路にアンパンマンやクレヨンしんちゃんの像が立っている。株式会社バンダイ本社の社屋が建ち、その前の歩道は、様々なキャラクターの像が立ち並ぶ“バンダイ キャラクター ストリート”と呼ばれている(その時は何の場所かわからず、後で調査してわかった)。女子生徒が走り寄り、ガラス越しに建物の中をのぞいている。

「ここの見学をしたい!」と言う生徒も。思わぬ臨時の休憩場所に。
14:14 臨時の休憩
水野先生からブルーベリーの飴が配布される。疲れると動けなくなるので、巡検のときには栄養補給のための「飴」を必ず用意されているのだ。

建物の中を見ようと走り寄って行った女子生徒は、アンパンマンが好きだとのこと。
ちょっとした休憩の後、目の前の「駒形どぜう」に移動して、記念撮影。
「駒形どぜう」はなんと本学の中等部の生徒の親御さんが経営しているそうだ。

巡検再開。

東京スカイツリーが見える交差点「駒形橋西詰交差点」に差し掛かると、「浅草に来たなあ」という実感が。

14:25 雷門に到着
ついに雷門が見えた。やはり存在感がある浅草の象徴だ。

1635年に創建され(942年という説もある)、火事などで再建を繰り返し、現在の形になったのは1960年。松下幸之助の寄進で建てられた。正式名称は「風雷神門」。

雷門の向かいにある浅草文化観光センターでトイレ休憩。外に置かれた「東京水」と書かれたウォーターサーバーで水の補充をする生徒たち。

「この建物の上階からは仲見世が見渡せて、撮影にも最適です」と小川先生が教えてくださった。

そして雷門をくぐり、仲見世を通って浅草寺へ。
平日にもかかわらず、噂通り外国人観光客であふれている。仲見世は日本で一番古い商店街の一つと言われており(一説に1685年)、その風情は国内外の人々を魅了し続けている。生徒が(自分が?)迷子にならないか心配だ。


その仲見世で、先生お二人が生徒のためにお菓子を購入。
かき分けかき分け、浅草寺に到着。
浅草寺の起源は628年と言われる。
「今から3・4分間の自由行動時間です。お参りする人、おみくじを引く人、行ってきてください」

半分の7人の生徒がお参りやおみくじに向かう。ほかの生徒は休憩、水分補給。
おみくじ組は、吉が3名、凶が2名。
小川先生が「浅草寺はほかと比べて凶がでる割合が高いんだよ。3割は凶」と励ます。
後日、浅草寺のウェブサイトを見たところ、比叡山延暦寺の良源僧正が広めたと言われるおみくじの原型「観音百籤(かんのんひゃくせん)」の伝統を受け継ぎ、大吉16%、吉35%、凶29%、その他20%という内訳だそう。
凶の2名は小川先生に導かれ、境内の結び所におみくじを結びに。


14:55 浅草今半前

「浅草寺は外国人が多かったですね。観光客の人数が増えている様子がうかがえました。これからかっぱ橋の方に進みます。かっぱ橋も、“日本の包丁が欲しい”といった外国人が多いでしょう。人気の食品サンプルもあります。業務用や家庭用などの調理道具もいろいろなものが揃っています。将来食品関係のお店を開きたい人は、ぜひ見てください」
途中、「かっぱ河太郎像」の前で記念撮影。

この像は2003年にかっぱ橋道具街の誕生90年を記念して、東京合羽橋商店街振興組合が建立したそう。この地帯は川の氾濫が多く、それを解消するために合羽屋喜八という人物が自費で掘割工事を開始。その進捗が芳しくないことを見かねた隅田川に住む、昔、喜八に助けられたことがある河童たちが夜こっそり工事を手伝って堀が完成した、という伝説がある、ロマンあふれる地。
「かっぱ」「合羽」「河童」。どれが正しいのだろうか。河童が居たからという説、小身の武士が内職で作った雨合羽を、天気の良い日に近くの橋にズラリと干していたからなど、諸説があるようだ。

「“かっぱ橋道具まつり”が開催されていて混んでいるので、周りに気をつけながら見ていきましょう。器や食器などのお店もあります。店によってお客さんの層も違います。この先に交番があるので、そこまで、右・左どちらの歩道を進んでもOKです。15:15に交番集合とします」


左側の歩道を行く水野先生と生徒のグループに同行。すると、とある道具屋さんに入っていく生徒が。お母さんの知り合いのご実家の道具屋さんだったそうで、ご挨拶に行ってきたとのこと。




水野先生が話された通り、包丁屋には外国人が目白押し。すさまじい熱気だ。
食品サンプルの店を見学すると、結構いい値がついている。おいしそうなイチゴパフェのサンプルが6000円ほど。
調理器具屋には、所狭しと様々な調理器具が並んでいる。店先の大きな寸胴鍋に目が行く。巡検が終わったら、調理道具を買いに行こう。
15:17 蔵前警察署の交番前に全員集合
少し疲れた様子の生徒たち。先生からのあんこ玉の差し入れを口に入れ、しばし疲労回復に没頭。笑顔が回復。

そして巡検再開。

頭上にはインパクトのあるコックさんの顔のオブジェが。
小川先生曰く「目の瞳の部分が鳩の形をしているんです」
本当だ!

仏壇のお店が立ち並び、お寺がたくさんある地帯へ。


「こちら側に仏具のお店が集中しています。なぜでしょう?」
生徒「日が当たると困るから」
正解。これまでの巡検での経験や学習が活かされているようだ。まさに北向きであった。神田の古書店街と一緒である。
「気がつかなかったかもしれませんが、先ほど東本願寺がありました。古い地図17番を見てください。東本願寺の隣に水路が通っています。今は水路はありません。この水路、かっぱ橋の河童に関係しているとかいないとか。来週の授業で今日の巡検をまとめたいと思います。3学期には浅草について、お店の分布図などを調べたいと思います。今日のレポートをまとめるホームページの担当者も決めましょう」
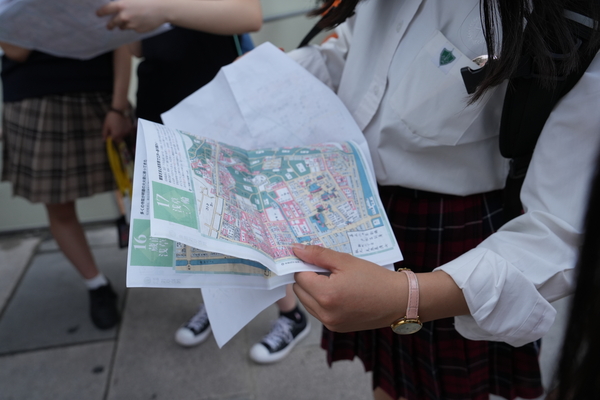
15:28 田原町駅で解散
およそ3kmの旅は終わりました。
取材班の一人は、調理道具を買いに行くこともできないほどクタクタに。
「江戸東京」の授業では、今年度、小川先生と水野先生がコラボし、ゲストスピーカーをお呼びして、歌舞伎や日本舞踊、長唄などの日本の文化を学んだり、巡検で、「渋谷・表参道」「四谷・永田町」「東京ジャーミイ」を訪れるなど、現物を間近で見て体験できる授業を展開している。授業後には生徒各人がレポートにまとめ、中等部ウェブサイトの報告記事を作成するなど、アクティブラーニングが実践されている。
そして、生徒の保護者や校友(卒業生)の方々の中に、日本の伝統文化を受け継ぎ、生業とされている方々がいらっしゃる。中等部への協力を快くお引き受けいただき、また生徒同士で繋がり、普段から日本の伝統文化を身近に感じることができるという贅沢な環境も備わっている。世界に羽ばたくためには、日本のことを世界の人に伝えられるように、世界の人々が関心を持っている日本の伝統文化の知識を身につけている必要があることは言を俟たない。
キリスト教教育を実践している一方で、多文化共生理解への実践的教育も行われている青山学院中等部。今の世の中で大切な、地球人としての在り様を生徒に考えさせる教育がなされていると実感した今回の取材だった。

