ハイ/ロー・カルチャー徒然帳〈6〉*この岩を踏みこの扉を通った老人たちもみな老いに怒号を吐いただろうか、私のように… 「バベルの塔」と老いと翻訳
2019/09/26

ブリューゲル「バベルの塔」展の最終日、酷暑と人混みを顧みず、上野の東京都美術館に出かけた。実際に足を運んだおかげで、いくつか自分の誤解を改めることができた。
まずこの絵の塔が、放置された後でなく、まさに建築途上の様子であること。東京藝術大学の同展関連プロジェクトが制作した精巧な複製画をじっくり鑑賞してはじめて、塔を建造し、塔に暮らす人々の姿が細密に描き込まれているのを確認できた。
また改めて『創世記』第十一章にあたってみると、ノアの子孫は「地の表に散ることを免れ」るために都=塔を建てようとし、一方神は人々が一箇所に固まるのを阻止するために言葉を乱したとされている。人間の傲慢への罰という解釈が先立ちやすいが、「地に満てよ」という神の命令の延長なのだと認識を改めた。
この絵からマーヴィン・ピークのゴーメンガースト城三部作を連想したのも今回が初めてだった。モダンファンタジーの中でも、迷宮めいた広大な城そのものが主人公であるような異色作である。第七六代城主セパルグレイヴ(墓の意の単語二種を組み合わせた名)とその息子タイタス・グローンの御代に進行する、若き反逆児の策謀が物語の主筋だ。登場人物はみな、石材と途方もない歳月の重みに押しつぶされたかのように奇妙に歪み、彼らの日常は複雑怪奇なしきたりに支配されている。「バベルの塔」に礼拝に向かう行列らしき一群が描き込まれているのを見て、塔の奥で幾世代も暮らした人々もやがてゴーメンガースト化したのではないか、などと空想した。
結局絵画「バベルの塔」は、言語が分化する以前の人間的活力を称揚した作と解釈するのが自然そうだが、翻訳が人々をつなげる理想状態のアレゴリーとして見る誘惑にも駆られる。かつてその博識に歯が立たなかったジョージ・スタイナーの大著『バベルの後に』に再挑戦してみようかと、珍しくやる気が出た。
翻訳という絵になりづらい素材を扱った珍しいドイツ映画が、ウクライナ出身の翻訳家スヴェトラーナ・ガイヤーに密着したドキュメンタリー『ドストエフスキーと愛に生きる』である(原題『五頭の象をつれた女』の象とはドストエフスキーの長編小説のこと)。文学と翻訳を語るガイヤーの活き活きした表情とは対照的に、買い物に出かけて料理を作る彼女の姿はとても老いて見えるが、たぶんそのように言葉から逃れる時間も大切なのだろう。スターリン・ヒトラー両独裁政権に翻弄された半生についてガイヤー自身の口は重く、その闇は計り知れないが、アイロンをかけながらメルヴィルの『白鯨』を語り、タイピングを手伝う友人らと茶を飲みながら作業するその日常には、こんな暮しもいいなと素直に思った。
映画『ドストエフスキーと愛に生きる』

監督・脚本:ヴァディム・イェンドレイコ
発売元:アップリンク
販売元:TCエンタテインメント
税抜価格:3,800円(DVD)
TCエンタテインメント 作品紹介ページへ
書籍『バベルの後に 言葉と翻訳の諸相』
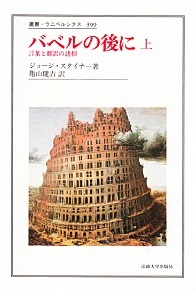
著者:ジョージ・スタイナー
訳者:亀山 健吉
出版社:法政大学出版局
刊行:上巻/ 1999 年3月 下巻/ 2009 年6月
税抜価格:上巻/ 5,000 円 下巻/ 6,000 円
法政大学出版局 書籍紹介ページへ