フィンランド 〜1年間暮らして考えたこと〜 【第10回】
2025/10/20
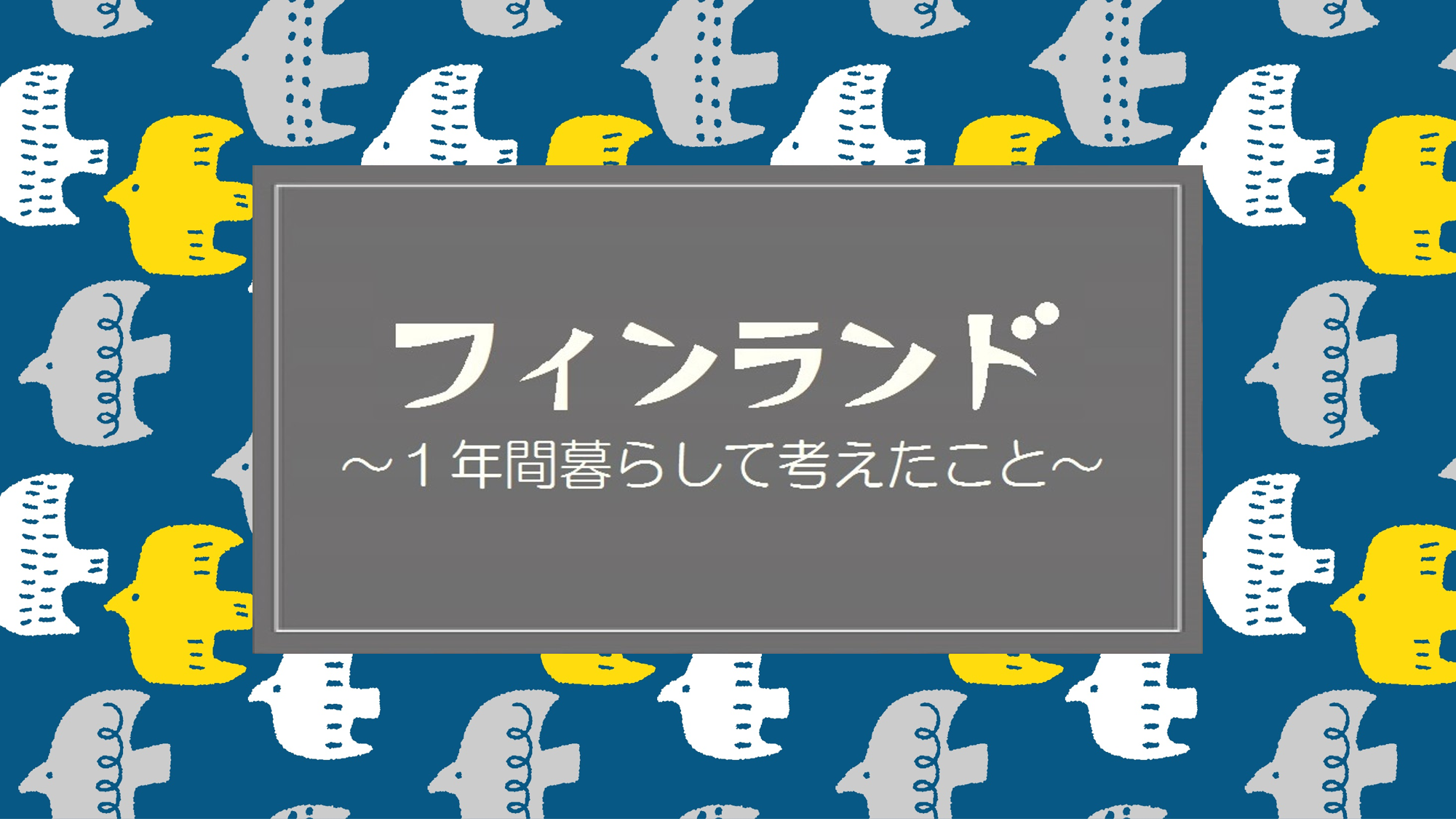
前回はジェンダー平等について書きましたが、今回は子ども・教育に関する平等・支援に関してフィンランド滞在中に印象的だったことを3つ取り上げたいと思います。
幼い子どもがいても、公共交通機関を利用して移動することに不便はあまりないようです。ヘルシンキの図書館Oodiでも、子どものコーナーにはベビーカーを置くスペースがたっぷりありますが、フィンランドでバスやトラムに乗っていると、ベビーカーをしばしば見かけます。これに関連してしばしば話題になるのが、幼い子どもをベビーカーでバスに乗せるときに、子どもだけでなく、子どもを連れている大人の運賃も無料になるということです。

このことについて、日本で誤った説明がされているのを目にすることがあります。「子育て支援」として、子どものいる家庭・親を経済的に支えるために、運賃を無料にしているという説明です。そのような背景もないわけではないのかもしれませんが、少なくとも公式に発表されているのは、安全上の理由なのです。
私が住んでいたタンペレのバスを例に説明します。通常、バスには前の入口から乗ります。運転席の付近に料金を支払う機械があり、バスのカードやスマホをタッチしたり、現金で支払ったりします。しかし、バスの前方の入口は狭いため、ベビーカーや車椅子は、バスの中央あたりの出入口を利用します。そこから乗るのは、ベビーカーや車椅子とその付き添いの人だけです。
この出入口から乗車した人は、どのように運賃を支払えばいいでしょうか。子どもが乗ったベビーカーを固定して、前の運転席のところに運賃を支払いに行くのでしょうか。バスの中に固定していたとしても、ベビーカーに乗った子どもから離れてしまうことは、短時間とはいえ、安全上の問題があります。このような安全面での合理的理由で、ベビーカーと共にいる大人1名は、運賃が免除されるのです。
その一方で、バスやトラムの中には、運転席の付近だけではなく中央の出入口付近にもスマホやカードをタッチする機械が設置されているものもあります。そのような場合は、ベビーカーの子どもを連れている大人も、運賃をそこで支払っているケースがほとんどです。また、子どもを抱っこして前の入口から乗車する人なども、運賃を支払います。
この事例から見えてくるのは、「弱者を保護すべき」「困っている人を支援すべき」といった、ある種の〝温かい〟感情論に基づいた支援とは異なる、フィンランドの考え方です。彼らは「誰もが安全に移動できる環境を整える」という合理的な視点から、公平かつ安心できる公共サービスを追求しているのです。
身体障害、発達障害、学習障害など、様々な障害のある子どもが学校に来ていますが、フィンランドではいわゆる健常児と共に障害のある子どもが学ぶ「インクルーシブ教育」が一般的です。クラスに学習障害や発達障害の子どもがいることは珍しくありません。そのような場合に、授業の担当の教員にプラスして、補助の先生が配置されます。どのような状態・特性の子どもが何人いるかということを点数化し、その点数に応じて教員の人数が決まっており、障害のある子どもがいるとそれに応じて支援の教員が配置されます。
ここで注意が必要なのは、「この子には障害があるから、この子個人を支援するための補助をつける」という考え方ではありません。「障害のある子どもがいるクラス全体に、教育・支援を行き届かせるために必要な人数の教員を配置する」という考え方です。様々な学校・教室で授業を見ていて、担任・担当の先生以外に支援の先生がいる場面もしばしば目にしました。しかし、どの児童・生徒に障害があるために支援の先生が入っているのかということは、ほとんどの場合全くわかりませんでした。
フィンランドでは、学校による差がほとんどありません。「フィンランドではどの学校に行っても基本的に同じ」ということは、教育学分野の大学教員からも、小学校・中学・高校の教員からも、一般の大人からも、よく聞きました。
日本の学習指導要領にあたるものはフィンランドにもありますが、大きな考え方・方針や目標を示すものであって、実際の授業や教材は、学校や教員によって異なります。それでも「どこに行っても同じ」というのは、「同じことをやっている」という意味ではありません。それぞれの学校や教員で工夫しながら、最終的にそれぞれの段階の学校を終えるまでに達成すべきことは、同じようにきちんと達成している(達成することになっている)ということです。
フィンランドでは公立学校がほとんどで、私立学校はごくわずかしかありません。ヘルシンキのインターナショナル・スクールなどは、多少の補助を受けているとはいえ、高額の学費が必要です。しかし、大部分の私立学校では、公立同様に政府からの補助金によって、学費は無料またはごくわずかの運営費がかかるのみです。
私の住んでいたタンペレにも、ドイツの哲学者・教育者であるルドルフ・シュタイナーの提唱した教育を実践している私立の「シュタイナー学校」があります。この学校も、学費は無料です。

公立・私立を問わず、すべての子どもが平等に質の高い教育を受けられるようにするというのが、1970年代の教育改革以来のフィンランドの政府や国民の考え方です。
もちろん、教育に割ける財源・予算は無限にあるわけではありません。そのため、新たな試みを導入したり、設備を整えたりするときは、優先順位をつけなければなりません。そのような場合に、「この学校はとても素晴らしい取り組みをして成果を出しているから、さらに充実させよう」という考えによるのではなく、「この学校は課題がより大きいから、まずここを充実させよう」という考え方が核になっています。
例えば、タンペレ市内で頻繁に訪れていた小学校が3校あります。そのうち2校は、戸建て住宅が多い落ち着いた住宅街にあります。ただ校舎は古く、教室内の机・椅子の配置なども「伝統的」な形で、「最先端」という雰囲気は感じられません。
もう1校は、集合住宅が多い地域にあり、移民の子どもも少なからずいて、その学校の教員の言葉を借りれば「社会的課題が小さくない」学校だということでした。しかし、校舎は新しく、校舎内のスペースや教室内の設備も、現代的な感じがします。たまたま校舎を新築したタイミングの問題かもしれませんが、すべての国民が等しく教育を受けられる環境を整えようとする考え方と無関係ではないのでは、と思いながらそれらの学校の様子を見ていました。

フィンランドの教育や子育て支援に見られる「平等・公平」の思想は、「誰もが社会の中で安全に、安心して、それぞれの能力を最大限に伸ばせるようにする」という、極めて合理的かつ実践的な考えに基づいていることを、こうした事例から強く感じました。