堀田季何先生の「めしませ、一句」【第3回 俳句の秘訣】
2025/08/04


2025年4月、雨の水曜日。新学期が始まったばかりの青山学院中等部――。
まだ真新しい校舎の5階の教室に、堀田 季何(ほった きか)先生の姿があった。
NHK俳句や「お~いお茶」をはじめとする俳句コンテストの審査員としても活躍される俳人だ。
中等部3年生選択授業「俳句」の授業のゲストスピーカーらしく、「俳句」についてスクリーンをバックに語っている。
何やら、興味深い話が聞こえてきた。

俳句には、ざっくり“いい句”と“微妙な句”があります。それは分かるんだけど、自分で作った句がいいか悪いか分からないことってありますよね。でも安心してください。俳句には“いい句”かどうかの判断方法があります。
それはずばり、書いてある17音以上に想像をかきたててくれる句です。
書いてあるままの句は「そうですね」で終わってしまう。でもその言葉以上に想像力をかきたててくれる、それが“いい句”のポイントです。

そして映像が浮かぶことというのもいい句であることが多いです。
“映像が浮かぶ”というと画を思い浮かべがちだけれど、別に視覚だけでなくて、聴覚でも味覚でも、どんな感覚でもいいから、「こういうシーンなんだ」と具体的に思い浮かべられること。
もし具体的に思い浮かべられたら、映像が浮かんだら、それはいい句であることが多いです。
逆に、当たり前のことを書いた句は“微妙な句”となってしまいます。
例えば
信号は僕も守るよ春の風
という句は、まるで交通標語のような印象しかしません。そして信号を守るのは、みんな当たり前ですよね。当たり前のことを書くのは俳句でなければ良いかもしれませんが、俳句としては“微妙な句”となってしまいます。

その他、見覚えのある句。キャッチコピーのように、どこかで見たなという印象を与える句も微妙です。
甲子園汗と涙のドラマ見る
この句は、甲子園で汗と涙を流すというのは夏の風物詩的光景です。
新聞の見出しには良いかもしれないけれど、どこかで見たような光景になってしまっています。
汗と涙は誰のものなのか、ピッチャーが最後にサヨナラを打たれて、泣き崩れてるのか、
汗をかきながら応援してる人たちの句なのか、檄(げき)をとばす監督なのか、汗みずくのホームランバッターなのか、具体的に思い浮かばないところも問題です。
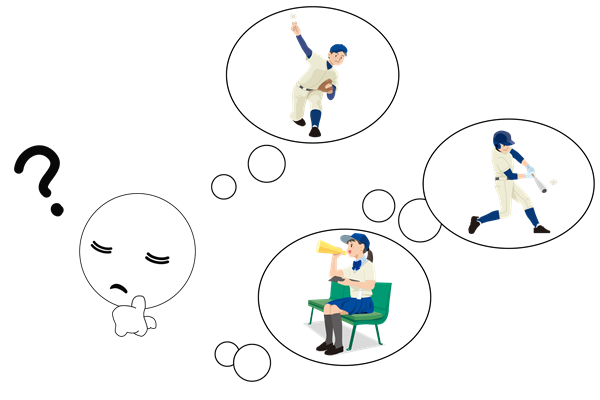
俳句が詠めたら、まず立ち止まって、詠んだ句をこんな視点で見てみましょう。
俳句の秘訣を身内に秘めておくと、普段見えている景色がよりビビッドに、そして視点も変わってくるはずです。
ぜひ自由に句を詠んでみてください。
「自由といっても本当に自由じゃないじゃない。 季語はあるし、季重なりは嫌うし」
という声が聞こえてきました。
では次回は、「自由不自由、俳句のあらゆる」をテーマにお届けします。