堀田季何先生の「めしませ、一句」【第4回 自由不自由、俳句のあらゆる】
2025/08/05


2025年4月、雨の水曜日。新学期が始まったばかりの青山学院中等部――。
まだ真新しい校舎の5階の教室に、堀田 季何(ほった きか)先生の姿があった。
NHK俳句や「お~いお茶」をはじめとする俳句コンテストの審査員としても活躍される俳人だ。
中等部3年生選択授業「俳句」の授業のゲストスピーカーらしく、「俳句」についてスクリーンをバックに語っている。
何やら、興味深い話が聞こえてきた。

「風流なものを作らなくちゃいけない」
とか
「自然を賛美しなくちゃいけない」
とか、なんてことはありません。
恋愛でも学校のことでも、両親と喧嘩しちゃったこととか、友だちと何か食べに行ったことや食べ物とか。もうなんでもいいんです。俳句で詠めないものなんてない。細胞でも、テレビのリモコンでもビッグバンでも宇宙でもなんでも詠めます。
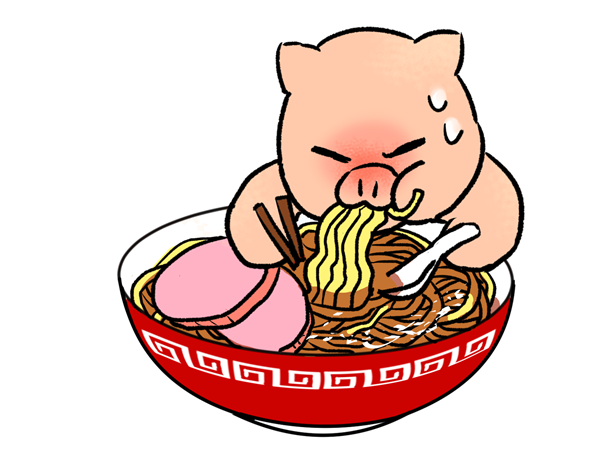
寝ていてもお風呂に入っていてもどんな時でも何をしていても詠める。

その上、道具や作法も必要ない。
ほら、すぐ身近にあることを(ないことでも)どんなことでも、どんどんじゃんじゃん詠んでください。
「えっ、季語が難しい?」
そもそもなぜ俳句に季語が入るのかというと、
俳句のそもそもの形が俳諧の連歌の最初の句、“挨拶みたいなものだったから”です。
私たちも、みんなで集まった時にまず挨拶から、「暑いですね」とか「寒くなりましたね」とか始めますよね。
時候の挨拶というくらい、どうしても季節の話題が多くなる。
だから俳句には季語が入ることが多いんです。
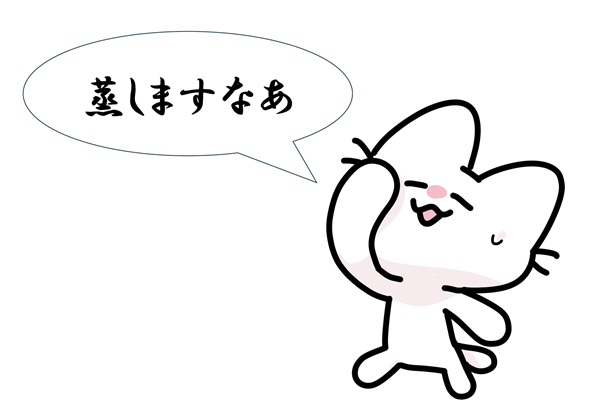
しかし例えば「ご愁傷様です」というお悔やみのシーンでは挨拶でも季節に触れないですよね。
「お父様がお亡くなりになりまして、今日は暑いですけど」
とはなりません。
挨拶によって季節が関係ない時があるのと同じです。
そんな季語ですが、季語の元になるような言葉はもう神話の時代から奈良時代、平安時代にかけてどんどん生まれてきました。
「桜と花は春を表す季語だ」とか、「月や鹿は秋、雪は冬だとか」かなりの数が季語になっています。
俳句に季語を入れるのを有季と呼びます。
ただ例外もあります。無季と言って季語の入らない句もあります。その他、季重なりと言って、季語を二語以上使う句もあります。
季重なりは通常嫌いますが、たくさん季語を使った句もあります。
目には青葉山ほととぎす初鰹 山口素堂
この句は、「青葉」「ほととぎす」「初鰹」と三つも季語を使っています。
このように、イメージが被らなければ良いでしょう。
例えば、
蟻(あり)と芍薬は両方夏の季語ですが、虫と花としてしまうより、具体的に書いた方がいいから許容だと思います。
でも蟻と夏の雨は許容範囲外です。蟻は夏の季語だから、夏の雨としなくても夏であることは分かります。
三音も無駄にしてしまうのではなく、蟻と雨の方が良いでしょう。
五七五で作る句を定型と言います。
この定型句のほか、七五五など定型以外の句もあります。これは自由律と言って、明治から大正時代にかけて誕生しました。日本では五七五で季語を入れる句、有季定型が人気ですが、世界では無季自由律が盛んです。
季語を入れないといけないとか、入れすぎちゃいけないとか、五七五でなくてはいけないとか
そこに囚われすぎず、句を詠んでみてください。
ただし、三段切れには注意しましょう。
春の暮自転車の錆(さび)丘の上
このように三つの名詞をただ並べただけの句は、ブツブツブツと三か所で切れ目があるように見えます。これが三段切れ。
そもそも「春の暮」「自転車の錆」「丘の上」と言われても、何が言いたいのか分からないですよね。つながりも脈絡もないフレーズを三つも出すのは損です。まずは一つか二つにフレーズを絞ってみると良いでしょう。