堀田季何先生の「めしませ、一句」【第6回 俳句誕生~②飛翔】
2025/08/18


2025年4月、雨の水曜日。新学期が始まったばかりの青山学院中等部――。
まだ真新しい校舎の5階の教室に、堀田 季何(ほった きか)先生の姿があった。
NHK俳句や「お~いお茶」をはじめとする俳句コンテストの審査員としても活躍される俳人だ。
中等部3年生選択授業「俳句」の授業のゲストスピーカーらしく、「俳句」についてスクリーンをバックに語っている。
何やら、興味深い話が聞こえてきた。

俳句は、俳諧の連歌という形で16世紀に始まりました。(ここまでの歴史を知りたい方は「俳句誕生~①黎明」をご覧ください)

時は流れて、江戸時代――。
松尾芭蕉や小林一茶とか、かの有名な俳人たちの登場です。
彼らの詠んだ句は、とても有名ですが、皆もれなく俳諧の連歌をやっていました。
「古池や蛙飛び込む水の音」
の五七五(発句)で有名な芭蕉ですが、発句よりもむしろ俳諧の連歌(連句)の方が得意だと言っています。
こうしてみんなで楽しく詠んでいたところ、それはそれでよかったのですが……
明治の頃、外国から来た人々に俳諧の連歌は、芸術とは違うものに映ったようで……
「なんかこれゲームだね」と、と捉えられました。

「いろんな人が、グループでやるようなものは、西洋の感覚からすると芸術ではない」と西洋の方々から言われたのです。
だからって気にせずに俳諧の連歌を続けていればいいのですが、当時の日本人はそれを真剣に受け止めました。それで俳諧の連歌の最初の句だけを独立させた。
こうして生まれたのが
近代俳句です。
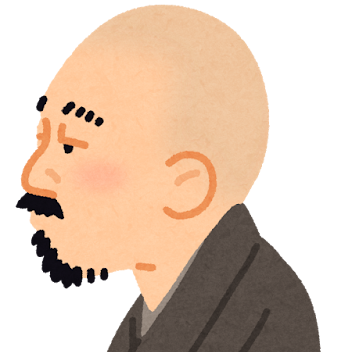
このように俳句には長い歴史があり、日本で生まれましたが、現在、世界中に広まっています。
俳句は、現在200 近くの国と地域で、200 近い言語で詠まれています。
太平洋のど真ん中のタヒチの、さらに先のマルキーズ諸島というところでも俳句を作っていますし、イラクでも作っています。またアメリカ合衆国の中学校の教科書には俳句が載っているほどです。
EU の初代大統領は、俳句が大好きで句集を出版していますし、アメリカの元大統領のオバマさんも俳句を作っています。
またケネディー家は詩が大好きらしく、キャロライン・ケネディさんが駐日米国大使(2013年から2021年まで)として日本にいらした時、一緒に句会をしたことがあります。
世界中で広まっている俳句ですが、俳句のノーベル賞第一号は日本人じゃないんです。
トーマス・トランストロンメルさんというスウェーデンの方がいらっしゃいますが、彼はスウェーデン語を使って、五七五で俳句を書いており、2011年に俳句を含む詩でノーベル賞をとっています。
さて俳句には、季語が入っているもの(有季)と入っていないもの(無季)があり、
日本では季語を入れ、五七五で詠む(定型)のが盛んですが、世界では季語がない(無季)俳句や、自由律と言って五七五ではない俳句の方が流行っています。
他の国の人からすると日本で季語と言っても、その国では季節が違うことがあります。
また五七五ではない自由律についても、例えば中国語で五七五だと長くなってしまう。漢字が17個も入ってしまうから、もっと短いのがいい、となるようです。
こうして世界各地で愛される俳句。この俳句のおかげで松尾芭蕉は世界で一番有名な俳人となっています。しかも最新の研究だと、世界で10番目ぐらいに有名な日本人だそうです。
定型でも自由律でも、有季でも無季でも、俳句のコンテンツ(詠む内容)は何でもいい。
両親と喧嘩しちゃったとか。友達とこれを食べに行ったとか。
細胞でも宇宙でもビッグバンでも。
なんでも詠めるのが俳句です。
ぜひ俳句を詠んで、そしてもし可能であれば句会に参加してみてください。